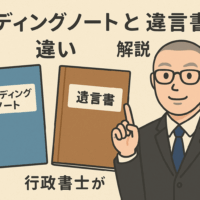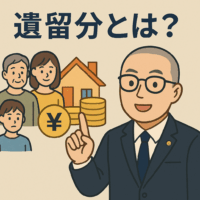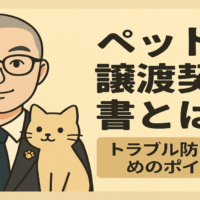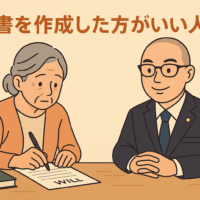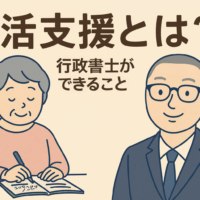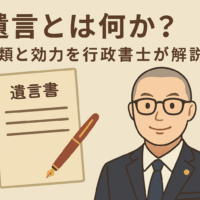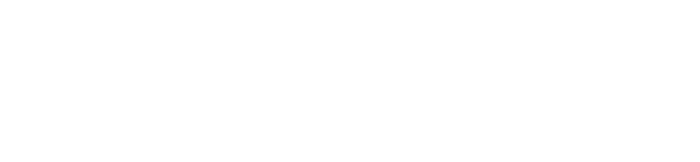- ホーム
- 権利義務に関する書類, 終活支援, 遺言書
- 自筆証書遺言の注意点~行政書士が解説~
自筆証書遺言の注意点~行政書士が解説~
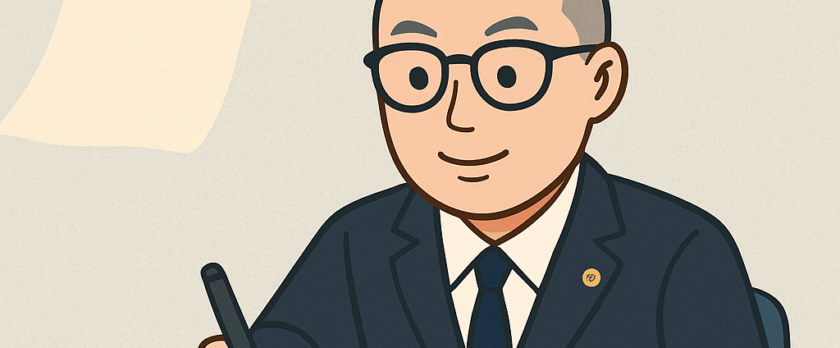
自筆証書遺言は、費用をかけずに自宅で作成できる手軽な遺言の方式です。
しかし、形式や内容に不備があると無効になるリスクもあります。ここでは、作成時の注意点を行政書士が解説します。
1. 全文を自書する必要がある
財産目録以外の本文は、パソコンやワープロでの作成は不可です。
日付・氏名も必ず手書きし、押印する必要があります(民法第968条)。
ただし、財産目録はパソコンなどで作成することもできます。また、登記事項証明書や預金通帳の写しを添付することもできます。
2. 日付は特定できる形で
「令和7年吉日」など曖昧な日付は無効になる可能性があります。
「令和7年8月1日」のように特定できる記載にしましょう。
3. 財産の特定は正確に
「自宅を長男に相続させる」だけでは不十分です。
不動産は登記事項証明書の記載通りに、預金は銀行名・支店名・口座番号まで明記したほうが混乱やもめ事の防止になります。
4. 法務局の保管制度を活用する
自筆証書遺言は紛失や改ざんの恐れがあります。
2020年からは法務局での保管制度が始まり、家庭裁判所の検認も不要になります。
5. 専門家のチェックを受ける
形式的に有効でも、内容が法律に反していると実現できない場合があります。
行政書士や公証人に相談して作成することをおすすめします。
6.意外な落とし穴
例えばご家族が亡くなった後に遺言書が発見されたとしましょう。その場合皆様ならどうしますか?一刻も早く中身を確認したくなりますよね。しかしそれはいけません。自筆証書遺言は、家庭裁判所にて検認という手続きをしなければなりません。検認はその相続人に遺言書の存在を知らせるとともに、形式が正しいかを確認し、偽造や勝手な変更を防止する手続きです。
📞 お問い合わせ
薬師行政書士事務所
電話:080-7845-6401
メール:yakushigyousei.2022@gmail.com
営業時間:平日9:00~18:00(土日応相談)
対応地域:栗原市・登米市・大崎市ほか宮城県北部